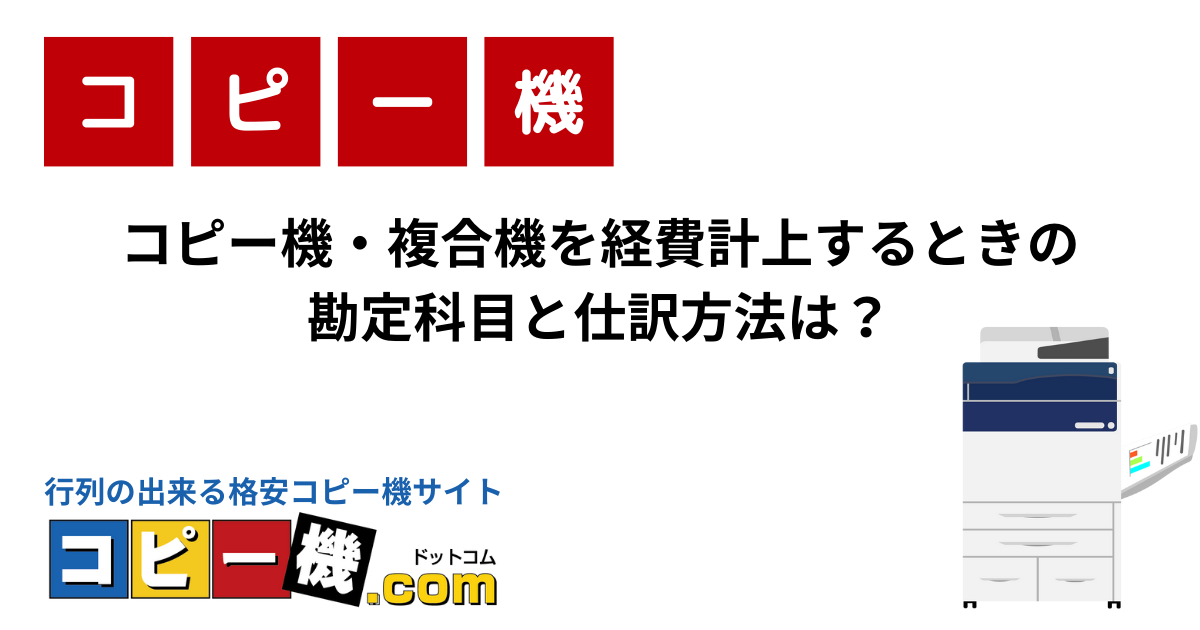目次
コピー機をオフィスに新たに購入したり、リースを利用し導入した場合でコピー機の勘定科目が異なることはご存知でしょうか?
さらにコピー機を購入した価格によっても勘定科目は異なり、リースの場合にもリースの取引形態によって勘定科目が変わってきます。
コピー機を導入したときの勘定科目を、購入とリースそれぞれのケース別に詳しく解説します。
コピー機・複合機を購入した場合の勘定科目
コピー機の勘定科目は「購入」と「リース」、「レンタル」で異なりますが、コピー機の「購入価格」によっても異なります。
適切な勘定科目に分類するためには、まずは購入したコピー機の価格を確認する必要があります。
購入価格によって「消耗品費」か「販売管理費」か「工具器具備品」に区分することができ、勘定科目を判断する価格は、10万円が一つのラインになります。
コピー機の購入価格が10万円未満の場合には勘定科目は消耗品費となり、コピー購入費用の全額を必要経費へ算入し一括経費とします。
それに対し、購入価格が10万円以上の場合には勘定科目は「工具器具備品」となり、固定資産に該当します。
この場合は購入金額を全額経費として計上することはできません。
耐用年数を5年とし減価償却する必要があります。
5年で減価償却するということは、経費ではなく資産として5年かけて資産価値を減らして費用計上するということです。
【参考1】一括償却資産の3年均等償却
コピー機の購入金額が20万円未満の場合は「一括償却資産の3年均等償却」として処理をすることができます。
一括償却資産とは資産勘定であり、購入にかかった費用が10万円以上20万円未満の減価償却資産の取得を行います。
その資産を3年間にわたり税務上の一括均等償却をする際に計上する勘定科目を指します。
ポイントとしては、この一括償却資産の3年均等償却を選択すると、勘定科目は「一括償却資産」となります。
決算時の処理として、金額の3分の1を「減価償却費」とします。
会社や法人が、一括償却資産の3年均等償却の適用を受ける場合には、
確定申告書などに「一括償却資産の損金算入に関する明細書」を添付して申告しなくてはいけません。
一括償却資産の3年均等償却を選択することには利点もありますが欠点もあります。
メリットとしては、通常の耐用年数5年よりも短い期間で費用計上が可能だという点です。
ただし、3年間の間にコピー機を譲渡や除却した場合にも、3年間は均等償却を続けなければならないというデメリットがあります。
メリットだけでなくデメリットも考慮する必要があります。
【参考2】中小企業等の特例
中小企業の場合には「中小企業等の特例」があります。
この特例を適用するためには、購入したコピー機が30万円未満だという条件があります。
さらに購入日にも条件があり、2020年3月31日までに購入したコピー機に限られます。
中小企業等の特例が適用されればコピー機の購入金額の全額を、購入した年に損金処理することが可能になります。
損金処理することができれば、会計上は費用として計上されるので課税対象外となります。
中小企業等の特例を適用することができる法人にも条件があり、青色申告法人の中小企業者、または農業協同組合などです。
さらに従業員の数が1000人以下でなくてはいけません。
中小企業等の特例を受ける場合の勘定科目の計上の仕方は、まず購入時には工具器具備品として資産に計上します。
その後の決算では同額を減価償却費として処理をするので、購入時と決算時の2回において計上処理を行うことになります。
さらに確定申告書などに「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して申告することが必要になります。
コピー機・複合機をリースした場合の勘定科目
コピー機をリースした場合の勘定科目は、コピー機を購入した場合とは違い「リース資産」となります。
取得時に資産として計上し、その際の金利はリース資産には含めません。
支払い時に支払利息として処理する必要があります。
リースには「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」があり、この2つは取引形態によって分けられています。
ファイナンスリースはリース取引期間中の契約解除ができないという特徴を持ち、それ以外のリースをオペレーティングリースに区分します。
ファイナンスリースはさらに細く区分され、「所有権移転ファイナンスリース」と「所有件移転外ファイナンスリース」で分けることができます。
所有権移転ファイナンスリースと所有件移転外ファイナンスリースでは勘定科目が異なるため、次項目以降で詳しく説明します。
所有権移転ファイナンスリース
所有権移転ファイナンスリースの大きな特徴は、リース期間を満了するとリースしていた資産を収得することができるという点です。
コピー機のリースの期間を終了すると、コピー機を貰い受けてそのまま使用することができます。
所有権がリース会社からリース先の会社に移行するため、リースを取得した時には勘定科目を「リース資産」として処理します。
支払い時には月額などを「リース債務」として費用計上しますが、この時は金利を含めません。
所有権移転ファイナンスリースでは、減価償却の処理の仕方は購入した場合と同じです。
所有権移転外ファイナンスリース
所有権移転外ファイナンスリースは、リース期間終了後にリースしていた資産をリース会社に返却する必要があります。
所有権移転ファイナンスリースとの違いは、リース期間終了後にリースしていたものを取得するか、
返却するかという点です。
コピー機のリースは、所有権移転外ファイナンスリースであることが多く、
取得時には勘定科目は「リース資産」として処理をします。
支払い時には「リース債務」を費用計上ししますが、
その際には「リース資産定額法」が適用されるため減価償却を行う必要があります。
具体的にはリース資産総額をリース契約期間の月数で割り、
事業年度ごとにその年度の契約月数分の金額を「減価償却費」として処理しなくてはいけません。
所有権移転外リースには特例で賃貸借処理が認められています。
中小企業がこの特例を適用するためには、リースの契約期間が1年以内であり、
リース契約1件あたりの総額が300万円以下であるという条件をクリアーする必要があります。
この条件をクリアし特例が認められると、コピー機を取得しても資産としてではなく、
リース料の支払金額を「リース料」として処理することができます。
コピー機・複合機をレンタルした場合の勘定科目
コピー機をレンタルした場合の勘定科目は「賃借料」として処理します。
レンタルとリースは似ているため混同されがちですが、この2つは契約形態が異なる全く別のものです。
契約の解除についても、「リースは取引期間中に解除することが不可能」であることに対し、「レンタルは契約期間中の解除が可能」です。
また契約の期間もリースは長期間の契約になりますが、レンタルはリースよりも短期間の契約であることが多いです。
企業や法人がコピー機を借りる場合はリース契約であることがほとんどですが、レンタル契約の可能性もあるということを念頭に置きましょう。
会計処理する際には自社の契約がリースなのかレンタルなのかを確認し、正しい処理をする必要があります。
コピー機・複合機の経費計上を正しく処理しよう!
コピー機の勘定科目は、購入価格やリース、レンタルなどによって異なります。
それぞれに条件や特例などがあるため複雑ですが、詳しく解説しましたので、会計処理の際の参考にしてください。
コピー機のことで何かお困りの際には、確かなメンテナンスと安心サポートを提供しているコピー機ドットコムに相談・お問い合わせください。
コピー機・複合機の導入なら「コピー機ドットコム」!
オフィスにコピー機を導入する際には、専門の業者を利用するとメンテナンスなどの管理が楽になり効率的です。
新しいコピー機への乗り換えや購入などの際には、コピー機や複合機の総合サイトのコピー機ドットコムへご相談ください。
コピー機ドットコムは業界最安値に挑戦しているため、リース料、レンタル料金が安くコストを抑えたい場合にピッタリです。
全国展開しているためコピー機の「不具合」や「故障」などのトラブルにも素早いメンテナンスが可能です。
365日24時間対応のため業務に支障が出ません。
トラブル発生時にはフリーダイヤルやチャットで相談を受け付けているので、サポート体制も万全で安心です。
コピー機ドットコムの運営会社である株式会社ビジョンは、オフィス用品提供サービスを行っているため、
コピー機だけでなくオフィス用品全般について相談できるので頼もしい味方になります!